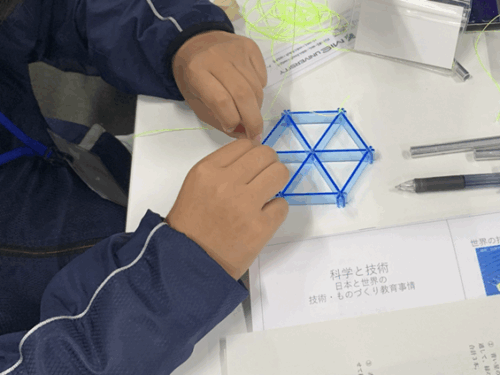エリアE(ヤマモリ株式会社):観察実験講座「地域の特徴があらわれる発酵食品 醤油 の魅力」が行われました
10月25日(土)に、ヤマモリ株式会社桑名工場にて、観察実験講座「地域の特徴があらわれる発酵食品 醤油 の魅力」が行われました。ヤマモリ株式会社 生産本部 桑名工場 製造部長 兼 醸造課長の大石様に、主にお話をいただきました。
まず、醤油がどのような工程で製造されているのか、ご紹介いただきました。醤油の主原料の1つとして大豆が使われます。丸ごとの大豆(丸大豆)を使った場合はまろやかでコクがある醤油に、油を絞ったあとの大豆(脱脂加工大豆)を使った場合は旨みが強くキレがある醤油に仕上がります。醤油の種類(こいくち、うすくち、たまり、さいしこみ、しろ)によって、材料となる大豆と小麦の割合が大きく異なることを説明いただきました。
醤油製造工程を、ご紹介いただきました。仕込み工程では、麹と冷却塩水を混合して諸味をつくり、雑菌の増殖を抑えます。かつて、この工程は気温が低い冬にしかできませんでした。発酵熟成工程では、適切に温度管理をして、冬春夏秋を再現します。伝統的には1年かけて熟成していた醤油の発酵熟成工程を、微生物が発酵能力を発揮できるように温度管理することによって、半年で実現できるようになりました。
加えて、日本の各地域で特徴のある醤油文化が育まれてきたことを紹介いただきました。特に三重県を含む東海地域では、料理によって醤油を使い分ける独自の食文化を持っています。たまり醤油やしろ醤油は、愛知県地域が発祥の醤油です。たまり醤油は小麦が少なく大豆が多いため旨味の強い醤油で、減塩効果や小麦を使用しないものはアレルギーフリーの観点で注目されています。
ヤマモリ株式会社では、三重県の大豆、小麦を使用して三重県で製造している再仕込み醤油「伊勢醤油」を製造しており、伊勢神宮に奉納していたり、伊勢志摩サミットの晩餐にも使用されていたことを紹介いただきました。
つづいて、醤油製造工場の一部を見学させていただきました。麹を作成する製麴工程や、もろみ発酵工程などを見学しながら、各工程での材料の化学的な変化について、説明をいただきました。
受講生は、「大豆にはタンパク質を多く含みアミノ酸に分解されます、そのおかげで醬油の旨味が出ている。そして小麦には、でんぷんを多く含み分解され糖分となり、醤油の甘みや、微生物のえさになったりする。」「醤油のおいしさを生む生物の中では、麹菌と酵母と乳酸菌がいる。その中でも、麹菌は大事で、この菌がなかったらいろんな食べ物がつくれない。酵母はアルコール発酵をしたりしていて、乳酸菌は、酸味があってさっぱりした味わいにする働きをしている。」といったこともまとめて、学ぶことができました。